大国主神(オオクニヌシ)兄弟殺害事件の全貌
兄弟による惨殺劇 — 日本神話に隠された残虐な物語
日本神話は美しい創世譚や英雄譚として語られることが多いですが、その奥底には現代のサスペンスドラマさながらの残忍な暗闇が広がっています。特に大国主神(オオクニヌシ)の物語には、兄弟による凄惨な殺害計画、執拗な迫害、そして復活という壮大なドラマが秘められています。
古事記と日本書紀に記された大国主神の物語は、単なる国作りの神話ではなく、家族間の嫉妬、権力争い、そして冷酷な謀殺という要素で彩られた血塗られた叙事詩なのです。
大国主神とは何者か?
大国主神は出雲の国(現在の島根県)を統治した神として知られていますが、彼の本来の名は「大穴牟遅神(オオナムチ)」でした。国土を統治する神となる前、彼は八十神(やそがみ)と呼ばれる多くの兄弟たちと共に暮らしていました。
ここで注目すべきは、大国主神が出雲の国を治める前の段階で、すでに兄弟たちとの間に深い亀裂が生じていたという点です。その原因は何だったのでしょうか?
殺害の動機 — 嫉妬と権力争い

古事記によれば、大国主神と兄弟たちは因幡(現在の鳥取県)へ旅をしていました。その目的は「八上比売(ヤガミヒメ)」という美しい女性を妻にすることでした。ここに最初の対立の種が蒔かれます。
兄弟たちは自分たちこそが八上比売の夫にふさわしいと主張していましたが、八上比売は大国主神に好意を抱いていました。さらに、大国主神は兄弟たちの荷物を運ばされる弱い立場にありながらも、旅の途中で出会った白兎を助け、その知恵と優しさを示していました。
これが兄弟たちの嫉妬心に火をつけ、大国主神への殺害計画が練られることになったのです。
残忍な殺害計画の実行
兄弟たちが実行した殺害計画は、その残忍さにおいて日本神話の中でも際立っています。彼らは大国主神を二度にわたって殺害しようと試みました。
最初の殺害計画:兄弟たちは山に赤い猪がいると偽り、大国主神を山へ誘い出しました。そして山の反対側から焼けた岩を転がし、それを猪だと信じた大国主神に抱かせて殺害しました。熱した岩を抱かされるという方法は、極めて残虐な手段と言えるでしょう。
二度目の殺害計画:大国主神の母神が息子を蘇らせると、今度は兄弟たちは彼を木の股に挟み、その上から大木を倒して圧死させるという方法を取りました。
これらの殺害方法からは、単に命を奪うだけでなく、苦しめ、辱めようとする意図が見て取れます。現代の犯罪心理学の観点から見ても、計画性と残虐性を兼ね備えた極めて悪質な事例と言えるでしょう。
神話に見る家族間暴力の象徴性
大国主神の兄弟による殺害は、単なる物語以上の意味を持ちます。この神話は古代日本における権力継承の争い、家族内の葛藤、そして社会的弱者への迫害を象徴しているとも考えられます。
考古学的証拠によれば、出雲地方では古代において権力闘争の痕跡が見られ、この神話はそうした歴史的背景を反映している可能性があります。
また、大国主神の殺害と復活という物語は、農耕社会における死と再生のサイクル、つまり種が地中に埋もれ(死)、やがて芽吹く(再生)という自然の摂理を表現しているとする解釈もあります。
しかし何より、この神話が示すのは、日本の神々もまた、ギリシャ神話やノルド神話の神々と同様に、嫉妬や憎しみ、権力欲といった極めて人間的な感情に支配されていたという事実かもしれません。
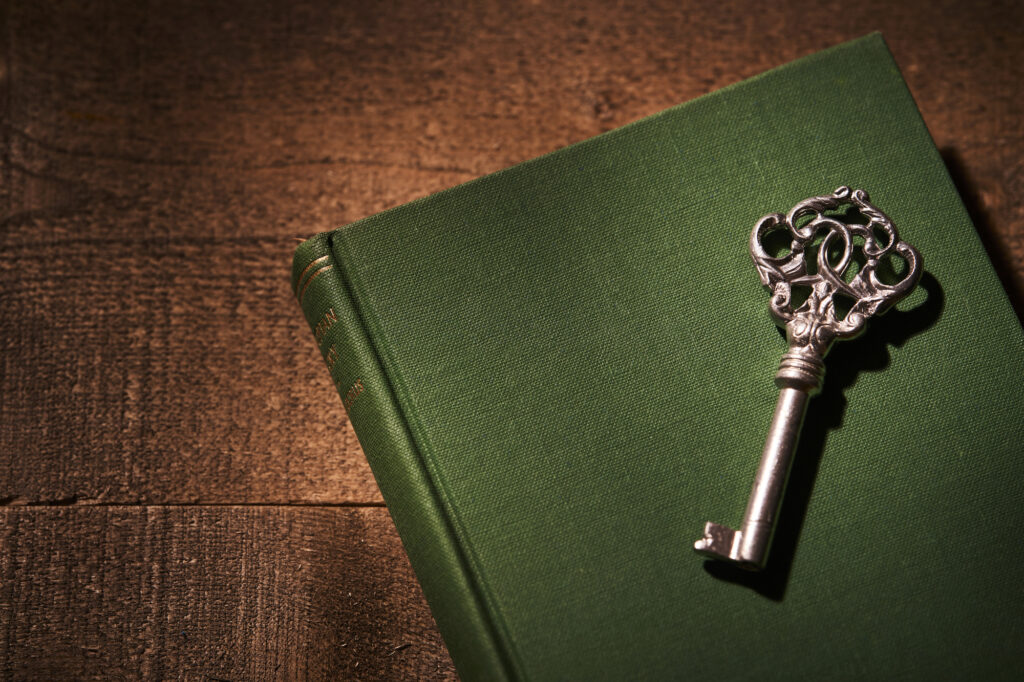
大国主神の物語は、彼がこの試練を乗り越え、やがて国土創成の神として偉大な業績を残すことになる壮大な叙事詩の序章に過ぎません。しかし、その出発点にある兄弟による残忍な謀殺は、日本神話の持つ意外な暴力性と複雑さを私たちに教えてくれるのです。
八十神による残忍な謀殺計画と実行の詳細
日本神話に登場する八十神(やそがみ)たちによるオオクニヌシ(大国主神)への謀殺は、古代日本の権力闘争を象徴する残虐な事件として知られています。この謀殺計画は単なる兄弟間の争いではなく、緻密に計画された残忍な暴力行為でした。
八十神の嫉妬と謀略の始まり
オオクニヌシは、父スサノオの娘ヤガミヒメとの縁組に成功し、その美しさと知恵で周囲から一目置かれる存在となっていました。これが八十神たちの激しい嫉妬を引き起こしたのです。『古事記』によれば、八十神たちはオオクニヌシの人気と影響力の高まりに危機感を抱き、彼を排除する計画を密かに練り始めました。
この謀殺計画は、日本神話における最も冷酷な権力闘争の一つとして描かれています。八十神たちは表向きは兄弟としての友好を装いながら、オオクニヌシの命を奪うための策略を練っていたのです。
謀殺計画の残忍な詳細
八十神たちが立てた計画は、その残虐さにおいて際立っています。彼らはオオクニヌシを伊耶那美(いざなみ)の国に誘い出し、そこで殺害する計画を立てました。具体的な謀殺方法は以下の通りです:
1. 赤熱した岩石の罠:八十神たちは大きな岩を赤熱し、それをオオクニヌシに向かって転がすという方法を考案しました
2. 狩猟を装った殺害計画:猪狩りを口実に、実際には大きな岩をオオクニヌシに向かって投げつける計画を立てました
3. 集団での襲撃:複数の神々が一斉にオオクニヌシを襲う計画も存在したとされています
考古学者の間では、これらの残忍な謀殺方法が当時の実際の権力闘争を反映している可能性が指摘されています。古代日本において、政治的ライバルの排除方法として、このような「事故」を装った殺害が行われていた可能性があるのです。
伯耆国での悲劇的な謀殺の実行
計画は伯耆国(現在の鳥取県西部)の大山(だいせん)で実行に移されました。八十神たちはオオクニヌシを山中に誘い出し、猪狩りを提案しました。彼らは「我々が山の上から猪を追い立てるから、お前は下で待ち構えていろ」とオオクニヌシに告げました。
しかし実際には、彼らは赤く焼いた大岩を「これぞ猪なり」と叫びながら山から転がし落としたのです。オオクニヌシはこの巨大な赤熱岩に押しつぶされ、その場で命を落としました。この残忍な謀殺シーンは、日本神話の中でも特に暴力的な描写として知られています。
考古学的調査によれば、大山周辺からは古代の祭祀跡が発見されており、この地域が実際に重要な神話的・宗教的場所であったことを示しています。これは日本神話 兄弟間の争いが単なる創作ではなく、実際の地理や歴史的背景に基づいている可能性を示唆しています。
オオクニヌシ殺害の象徴的意味
この残忍な謀殺には、単なる兄弟間の争い以上の深い意味が込められています。歴史学者や神話研究者たちは、この事件を以下のように解釈しています:
– 政治的権力闘争の象徴:出雲の国(現在の島根県東部)の支配権をめぐる争いの象徴
– 農耕神としての死と再生:オオクニヌシの死と復活は農耕神話における豊穣のサイクルを表している
– 古代氏族間の対立:実際の氏族間の争いが神話に反映された可能性
特に注目すべきは、この残忍な謀殺の後にオオクニヌシが復活することです。これは彼の神としての力を示すとともに、後の国造りにおける彼の中心的役割への伏線となっています。
日本各地に残る伝承では、オオクニヌシ殺害の物語はさらに残酷な詳細を含むバージョンも存在します。例えば、八十神たちが彼の遺体を切り刻んだという伝承や、母神が息子の体を寄せ集めて復活させたという話もあります。これらの残虐な描写は、古代社会における権力闘争の激しさを物語っていると考えられています。
このように、オオクニヌシの殺害は日本神話における最も残忍な謀殺事件の一つとして、今日まで語り継がれているのです。その物語は古代日本の政治的・宗教的背景を理解する上で重要な手がかりを提供しています。
日本神話に隠された兄弟間の権力闘争と血の因果
日本神話の表舞台に描かれる英雄譚の影には、常に権力闘争と血で血を洗う残酷な物語が隠されています。大国主神(オオクニヌシ)の物語もまた例外ではありません。古事記に記された彼の数奇な運命は、単なる神話を超え、古代日本の政治的・社会的構造を映し出す鏡となっているのです。
八十神(やそがみ)の嫉妬と権力への渇望
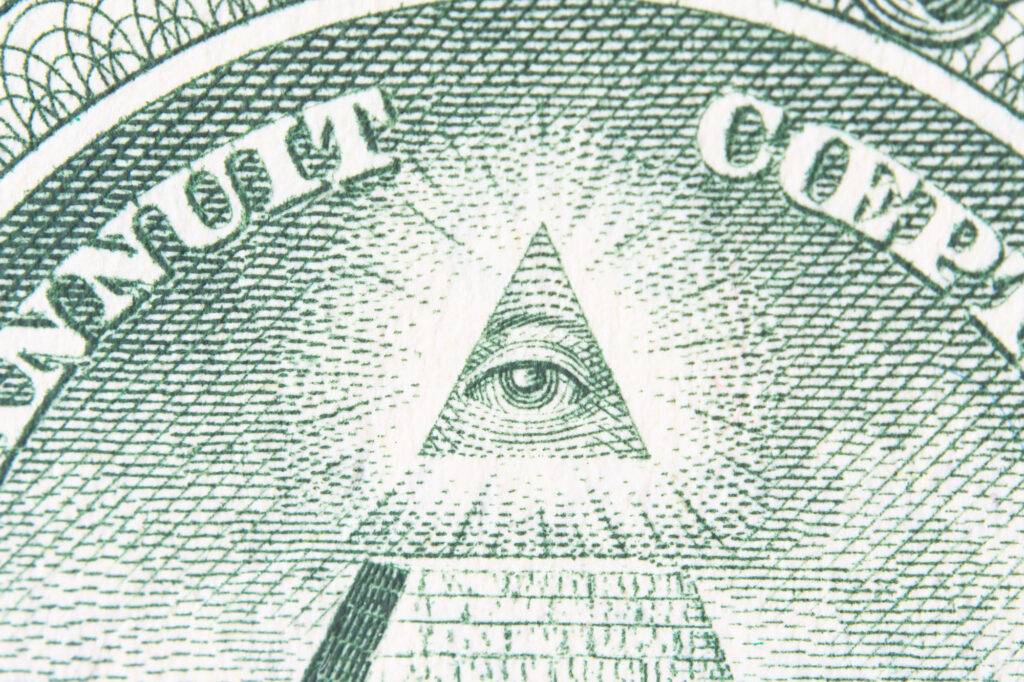
大国主神(当時の名は大穴牟遅神/オオナムチ)が兄たちから受けた迫害は、一般的な兄弟げんかの域を遥かに超えています。八十神と呼ばれる多数の兄弟たちは、なぜここまで残忍な謀殺計画を立てたのでしょうか。
その背景には、因幡の白兎伝説に見られる大国主神の慈悲深さと知恵が関係しています。白兎を助けた彼の行為は、単なる善行ではなく、政治的な意味合いを持っていました。白兎(実は神の使い)を救済したことで、彼は神聖な存在として認められ始めたのです。
この評判の高まりこそが、兄たちの嫉妬を掻き立てる原因となりました。古代社会において、カリスマ性と民衆からの支持は権力の源泉。八十神たちはオオナムチの人気上昇を、自分たちの地位への脅威と捉えたのです。
史料によると、この時代の出雲地方では、複数の氏族間での権力闘争が激化していました。考古学的発掘からも、この時期に出雲地域で武力衝突の痕跡が見つかっています。神話は、こうした歴史的背景を象徴的に表現したものかもしれません。
殺害計画の残忍性と象徴的意味
兄弟たちによる殺害計画は、その残酷さにおいて日本神話でも特筆すべきものです。彼らは単に殺すだけでなく、その方法に特別な意味を込めていました。
最初の殺害計画では、彼らは真っ赤に焼けた岩石を転がし、それをイノシシだと偽ってオオナムチに抱かせるという手段を取りました。これは以下の象徴的意味を持っています:
1. 火による浄化と排除 – 古代信仰において火は浄化の象徴であり、敵対者を完全に消し去る手段
2. 欺瞞による殺害 – 直接的な暴力ではなく、騙しによる殺害は政治的陰謀の象徴
3. イノシシの偽装 – イノシシは豊穣と力の象徴であり、これを偽ることで大国主神の豊穣神としての性質を否定する意図
さらに、二度目の殺害では、大木の割れ目に挟んで殺そうとしました。これは:
1. 自然の力を利用した処刑 – 神としての力を持つ者を自然の力で打ち負かす象徴
2. 木による処刑 – 木は生命の象徴でありながら、ここでは死の道具となる皮肉
3. 挟み込むという方法 – 社会的に追い詰められ、逃げ場のない状況の象徴
これらの殺害方法は単なる物理的暴力を超え、政治的・宗教的な意味合いを持っていたと考えられます。
日本神話における兄弟殺しの系譜
大国主神の殺害未遂事件は、日本神話に見られる兄弟間の権力闘争の一例に過ぎません。実は日本神話全体を通して、兄弟間の争いと殺害のモチーフが繰り返し登場します:
– イザナギとイザナミの子である火の神カグツチの誕生と殺害
– 天照大神と須佐之男命の確執
– 海幸彦と山幸彦の争い
これらの神話に共通するのは、単なる個人的な争いではなく、異なる価値観や文化、政治勢力の衝突を象徴している点です。大国主神の物語もまた、出雲と大和の政治的関係性を反映していると考えられています。
考古学者の佐々木高明氏の研究によれば、出雲神話のこうした暴力性は、古代日本における政治的統合過程の痛みを表現したものだとされています。実際、出雲地方から発掘される青銅器には、戦闘や権力の象徴が多く含まれているのです。
大国主神が兄弟たちの殺害計画から生き延び、最終的に国作りの神として称えられるようになった背景には、出雲と大和の政治的和解、あるいは統合のプロセスが反映されているのかもしれません。日本神話に隠された兄弟間の血の因果は、古代日本の複雑な政治状況を理解する重要な手がかりとなっているのです。
よみがえる大国主神 – 死と再生の神秘的物語

死と再生は多くの神話に見られるモチーフですが、大国主神(オオクニヌシ)の物語における「死と再生」のエピソードは、日本神話の中でも特に神秘的で象徴的な意味を持っています。兄弟たちによる残忍な謀殺から蘇った大国主神は、単なる復活ではなく、神としての力を増し、より強大な存在へと変貌を遂げていきます。
白兎の恩返し – 復活の契機
大国主神が兄弟たちによって殺害された後、彼の母神である刺国若比売(きさがいわかひめ)が嘆き悲しみ、高天原に救いを求めました。これに応えて派遣されたのが、神産巣日神(かみむすびのかみ)の娘である奇稲田姫(くしなだひめ)と蓁芽田姫(うがやたひめ)です。
彼女たちが持参した「生き返らせの薬」によって大国主神は蘇生しました。この復活は単なる物語の展開ではなく、死と再生を通じた神格の変容を意味しています。興味深いことに、この復活には因幡の白兎との関わりも示唆されています。
大国主神が因幡の白兎を助けた善行が、後に自身が危機に瀕した時の救済につながったという解釈もあります。日本神話における「善行の報い」という道徳的メッセージが込められているのです。
死を超えた神の力 – 変容するオオクニヌシ
復活後の大国主神は、それまでとは明らかに異なる神格を持つようになります。「国作り」「国譲り」の神話で中心的役割を担うようになるのは、この復活後のことです。
復活前:
– 兄弟たちに従う立場
– 比較的弱い存在
– 神格としての明確な役割が不明確
復活後:
– 国土を治める力を持つ
– 須佐之男命から力を授かる
– 国譲りの主体となる強大な神
この変容は、日本神話における「死と再生」のテーマが単なる物語の装飾ではなく、神の力の源泉や変化を説明する重要な要素であることを示しています。
死と再生の神秘的意味 – 古代日本人の世界観
大国主神の死と再生には、古代日本人の死生観が色濃く反映されています。死は終わりではなく、より高次の存在への移行過程と捉えられていたことがわかります。
特に注目すべきは、大国主神が死から蘇った後に「国作り」の神としての役割を担うようになる点です。これは「死と再生」が単なる生物学的な現象ではなく、神聖な力の獲得や神格の変容と結びついていたことを示しています。
古代日本人にとって、死と再生のサイクルは自然界の循環を象徴するものであり、農耕社会における豊穣と結びついた重要な概念でした。大国主神の物語はこの世界観を神話として具現化したものと言えるでしょう。
他の神話との比較 – 普遍的テーマとしての死と再生
大国主神の死と再生の物語は、世界各地の神話に見られる「死と再生」のテーマと共通点を持っています。
– エジプト神話のオシリス:セトによって殺害され、イシスによって復活させられる
– ギリシャ神話のディオニュソス:ティタン族に殺されるが、再び生まれ変わる
– メソポタミア神話のイナンナ/イシュタル:冥界に降り、死から復活する
これらの神話と比較すると、大国主神の謀殺と復活の物語は、より政治的な文脈(国土の支配権)と結びついている点が特徴的です。また、復活後に「国作り」という創造的役割を担う点も、日本神話ならではの特徴と言えるでしょう。
大国主神の死と再生の物語は、単なる残忍な兄弟による謀殺という暴力的エピソードを超えて、古代日本人の宇宙観・死生観を反映した深遠な物語です。そこには、試練を乗り越えた者が真の力を得るという普遍的なメッセージが込められています。現代に生きる私たちにとっても、挫折や苦難を乗り越えた先に真の成長があるという示唆に富んだ神話と言えるでしょう。
古事記と日本書紀に描かれた殺害シーンの違いと歴史的解釈
古事記と日本書紀の描写の違い
大国主神(オオクニヌシ)の殺害シーンは、古事記と日本書紀で興味深い違いを見せています。古事記では、兄弟たちによる殺害は生々しく描かれ、特に「赤熱した石を抱かせる」という残虐な手法が強調されています。一方、日本書紀では同じ出来事がより政治的・象徴的な表現で記述され、直接的な暴力描写が抑えられています。

古事記の記述:
– 大勢の兄弟が共謀して罠を仕掛ける様子が詳細に描かれる
– 「赤く焼けた岩を抱かせる」という具体的な殺害方法
– 大国主神の苦しみが強調される表現
日本書紀の記述:
– より簡潔で象徴的な表現
– 政治的対立としての側面が強調される
– 神話的要素よりも歴史的記録としての性格が強い
この違いは、両書の成立目的と編纂方針の違いを反映しています。古事記(712年成立)が神話としての性格を強く持つのに対し、日本書紀(720年成立)は中国の正史を模した歴史書としての性格が強いためです。
歴史学者による解釈の変遷
大国主神の殺害シーンに関する歴史的解釈は、時代とともに変化してきました。
戦前の国学者たちは、この物語を文字通りの神話として解釈し、大国主神の苦難と復活を日本民族の強靭さの象徴として位置づけました。しかし現代の歴史学では、この神話を古代出雲と大和の政治的対立の象徴として解釈する見方が主流です。
考古学者・松本健一氏は「大国主神の殺害神話は、出雲地方の在来勢力が大和朝廷に征服される過程を象徴的に表現したものだ」と指摘しています。また民俗学者・吉田敦彦氏は「兄弟による殺害は、農耕儀礼における再生と豊穣のモチーフを含んでいる」と分析しています。
近年の研究では、テキスト分析と考古学的証拠を組み合わせた新たな解釈も提示されています:
– 大国主神の殺害と復活は古代の権力移行の儀式を反映している
– 「赤熱した石」は製鉄技術の隠喩である可能性
– 兄弟間の争いは、実際の氏族間の政治的抗争を象徴している
地域による伝承の違い
日本全国に残る大国主神伝承を調査すると、地域によって殺害シーンの描写に興味深い違いがあります。
出雲地方では、大国主神(ここでは主に「大己貴命」として)は被害者というより英雄として描かれ、兄弟たちの仕掛けた罠をかいくぐる賢明さが強調されます。一方、大和地方の伝承では、より政治的な文脈で語られる傾向があります。
地域別の特徴的な伝承:
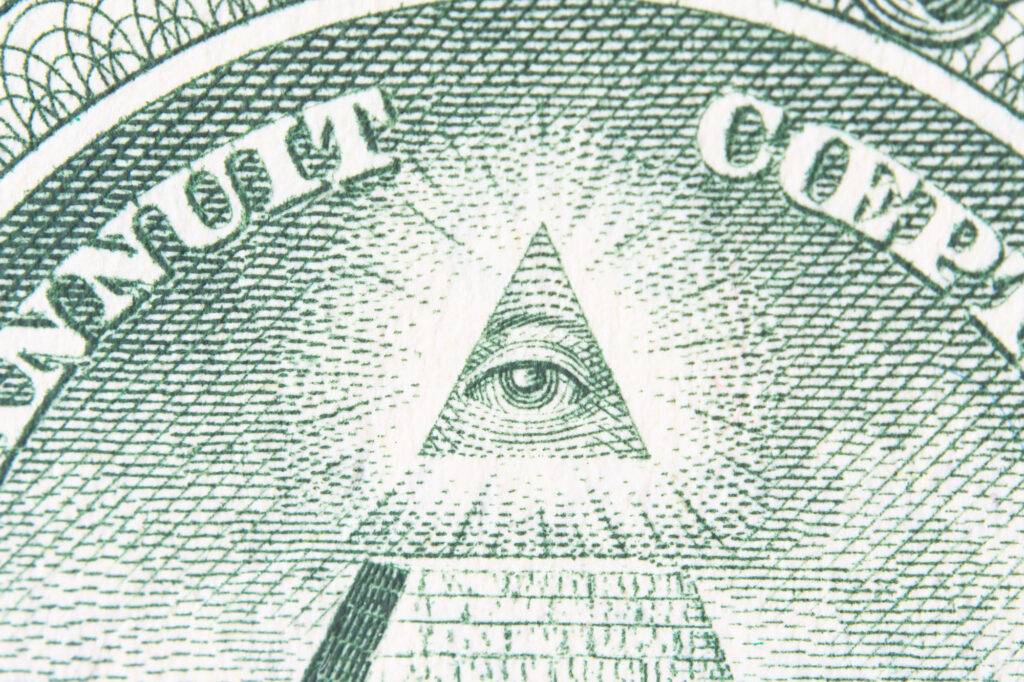
| 地域 | 殺害シーンの特徴 | 解釈の傾向 |
|——|—————-|————|
| 出雲 | 復活と再生が強調 | 農耕神としての側面 |
| 大和 | 政治的抗争として描写 | 王権交代の象徴 |
| 北陸 | 製鉄技術との関連 | 技術伝播の神話 |
| 九州 | 海外との関連性を示唆 | 大陸文化の影響 |
特に注目すべきは、出雲地方に残る口承では「オオクニヌシ 殺害」の場面が、死と再生のサイクルとして肯定的に解釈される傾向があることです。これは農耕社会における季節の循環と結びついた世界観を反映していると考えられます。
現代における神話解釈の意義
大国主神の殺害神話は、単なる残忍な「日本神話 兄弟」間の争いの物語ではなく、多層的な解釈が可能な豊かなテキストです。現代社会においても、この神話は権力、家族関係、死と再生といった普遍的テーマを考える上で重要な示唆を与えています。
この「残忍 謀殺」の物語が千年以上にわたって語り継がれてきた理由は、それが単なる暴力的エピソードではなく、社会の深層構造や人間心理の普遍的側面を反映しているからでしょう。大国主神の物語は、権力闘争、嫉妬、復讐、そして最終的な和解と国土創成という、人間社会の根本的なドラマを象徴的に表現しています。
古代の神話は、現代の私たちが直面する課題—権力の正当な継承、家族内の葛藤、暴力と和解—を考える上での貴重な鏡となります。大国主神の殺害と復活の物語は、日本文化の根底に流れる死と再生、破壊と創造の弁証法的理解を示す重要な文化的資源なのです。
ピックアップ記事





コメント